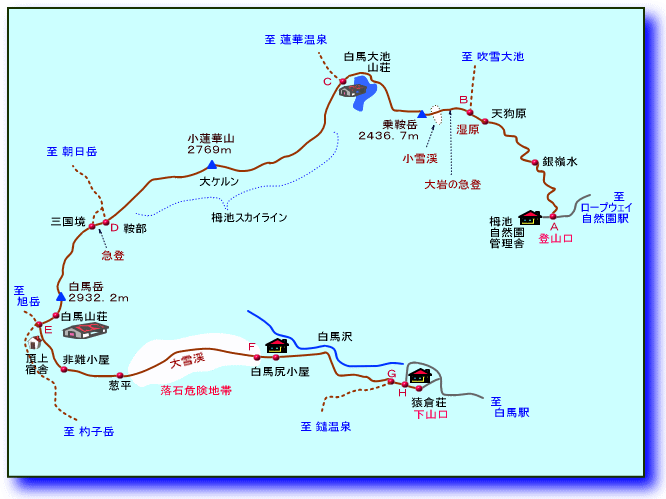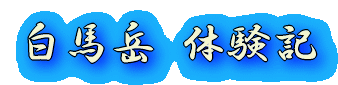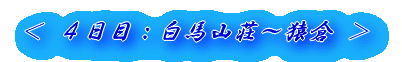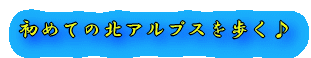AM3時過ぎに起き出して外に出てみると
昨夜の雷雨が嘘のように星空が広がっているではないか\(^o^)/
5時に開く食堂前に4時半に行くと既に10名程度が並んでいる。
朝食は食堂入口に並んだ順になる。
ツアー客は人数が多く、添乗員指示で動くので
出遅れて、この後に並ぶと朝食がAM6時半などになり
その日の行動に影響が出る。(要注意)
歓声が上がるのでそちらを見ると
食堂の窓から“剣岳”の雄姿が見えるが生憎カメラを持ってきてない(>_<)
部屋に大急ぎで戻り窓から撮したが「時すでに遅し」・・・5:26
山頂に雲がかかっている。
|

6:04
外に出てガビーンといった感じだ。
何と先ほどまでの様子が嘘のように霧が出ているではないか(>_<)
次々に出発する登山客を見送りに出てきていた
山荘スタッフに“猿倉”までのコースの様子を聞くと
「特に迷うところは無いですよ」とのこと。
その言葉に少し安心して、後押しされるように下山を開始することにする。
|

6:16
“頂上宿舎”手前の分岐標識まで下ってきた。・・・(E地点)
前を直進して進むのは“杓子岳”方向へ縦走する
全員60代と思われるツアーの団体だ。
これほど霧が濃くては縦走もキツイばかりで楽しくないだろう(^_^;)
|

我々は左折して“頂上宿舎”の前を下る。
いずれにしても初めて歩く道
道が大きくカーブしているのでコンパスは使い憎い。
コースを外さないように慎重に下るしかない。
|

6:40
枕木の階段は横向きに滑る。
身体を横にして一歩一歩慎重に下る。
|

少し明るくなってきたか。
|

周囲はお花畑だが、先行き不安で正直ジックリと撮影する余裕無し(^_^;)
|

6:46
前方に登山者が見えた。
どうやらルートは間違ってなかったようだ♪
“白馬大池山荘”で知り合いになった6人グループだ。
中には久留米や宗像出身の方がおられて
我々が福岡から来たとゆうことで話が弾んだ方達だ♪
|

麓方向から沸き上がって来るような霧が何とも迫力がある。
|

足場の悪い道を慎重に下る。
|

道が間違ってなかったことが判り一安心。
周囲の花を眺める余裕も出てきた♪
|

7:11
建物が現れた。
“非難小屋”だ。
|

7:16
右手に雪渓が現れた。
“小雪渓”だ。
|

ガイドブックの説明では一般的には
“小雪渓”を横切るようにルート設定されているらしいが
“小雪渓”の方は道が荒れている。
暫く様子を確認していると下の方に登って来た登山者の姿が見える。
標識から下に向かって真っ直ぐに下るようになっているようだ。
この辺りがルートが一番判り辛かった。
雪渓の状況を見てコース設定が変わるらしい。
下山中、“葱平”の標識は目に入らなかった。
|

“大雪渓”の下りは落石要注意なのは承知していたが
その前の岩だらけの道も侮り難い。
振り返って見上げると、
どの石もいつ転がり始めてもおかしくない石ばかりだ/(・_・)
|

フト傍らに目をやるとクルマユリの朱色が一際鮮やか。
|

7:41
眼下に“大雪渓”が見えるようになってきた。
イヨイヨ、日本三大雪渓を下るかと思うと気合が入る。
|

7:45
“大雪渓”が更に近づく。 |

“大雪渓”を右に見ながら進む。
|

左手にデカイ落石が現れた。
不気味な感じの赤い岩だ。
更に落ちないように廻りにネット階段を設けて養生しているように見える。
こんなのが転がったら、それこそ大事になりそうだ/(・_・)
|

ここの横断も結構怖かった。
左手を見上げると
いつ落石が起きてもおかしくない場所だ。
|

“大雪渓”の上流の端の一部。
厚さは1m以上はあるようだ。
|

8:07
ようやく“大雪渓”の取り付き点が見えてきた。
雪渓の中央を登ってきて、直角にこちらの山腹に取り付いている。
|

狭い道での離合が増えて中々前に進まない。
足を滑らせて落ちたら大事になる。
慎重を要する歩きが続く。
|

8:30
“大雪渓”の取り付き点まで下りてきた。
安全と思われる場所に座ってアイゼンを装着する。
突然「ラクっー、ラクっー」と叫ぶ声
バスケットボール大の石が右手から雪渓まで転がってきた。
ビビルには十分の光景だ(>_<)。
|

周りを見るとアイゼン装着に手こずっている方もかなりいる。
初めてアイゼンを使う登山者も結構いるようだ。
自分には到底考えられない(笑)
皆さんいい度胸をしている。
しかも2本爪が多い。
2本爪での下りは厳しいと思うのだが・・・・・
(白馬館のレンタルも2本爪だったようだ)
|

8:36
イヨイヨ、“大雪渓”の下りを開始する。
そこら中に転がった石に恐怖感を感じる。
霧で視界が無いのが更に恐怖感を増す。
|

8:43
ここら辺りに落石はないようだ。
「撮しましょう」の声に、顔は笑っているが
内心では少々ビビリながらポーズをとる(^_^;)
|

かなり霧が晴れて周囲の様子が判りだした。
|

離合の際に踏み跡の無い脇に道を譲ったときに
2本爪は滑って、うまく下れないようだ。
おのずと離合待ちの時間が増える。
6本爪は滑らないので周囲を見る余裕があって良い。
|

左手の土が剥き出しの島で登山者が休憩している。
小石なら安全か?
雪渓の平均斜度は20度程度か?
それでも6本爪でも油断すると滑る、30度近くありそうな箇所もあった。
|

デカイのが転がっている。
|

離合停滞中にチョッと振り向いて
|

「雪渓上にある石は全部落ちてきた石です
早く大雪渓を通過して下さい」のプレート |

それにしてもこの登りは相当にきつそうだ。
全員足下を見ながら黙々と歩いている。
笑顔無し・・・・・修行のようだ。
中にはかなり疲れた様子で本当に山頂まで行けるのかと
人事ながら心配になる方も見受けられる。
軟弱登山者としては下山に使って大正解だった(^_^;)
通過時間も1時間以上短いので下りの方がかえって安全かも知れない。
|

一旦、霧が出たが又晴れてきた♪
|

9:33
下り始めて約1時間・・・・・
かなり下ってきたはずだが周囲にはまだ落石がある。
“大雪渓”は全体が危険箇所と考えた方がいいようだ。
|

霧の中に突入するように黙々と登っていく単独登山者。
|

終点間近だが、まだデカイのが転がっている。
|

これもデカイ。
|

9:48
下り始めて約1時間10分・・・・・思いのほか早く通過できた。
“大雪渓”の終点(F地点)まで降りてきた♪
ほぼ、ノンスリップで下れた。
やはり、ダブルストックと6本爪の威力は絶大だった。
|

無事に下れた喜びと安堵感を全身で表す\(^o^)/
両サイドの崖の様子を見ると
“大雪渓”で落石に会うか会わないかは
運次第といった感じだった。
|

“大雪渓”方向を眺めて
イヨイヨ、白馬ともお別れかと感慨に浸る。
|

9:55
“白馬尻小屋”に向けて下る。
先ほどまでの涼しさが嘘のように暑い。
|

左手に水量の少ない“白馬沢”を眺めながら歩く。
|

木道を進む。
|

10:08
“白馬尻小屋”に到着する。
無事に下山して安堵感に浸る者、
これからの登りを控えて心の準備をする者、
皆さん、思いは様々のようだ。
|

渓谷に敷かれたホワイト・カーペット・・・・・
あれを下って来たのかと再度感慨に浸る。
|

10:23
今度は下山口の“猿倉荘”に向けて出発する。
マップを見ると50分程度で着けるはずだ。
|

木道が設置されて良く整備されている♪
|

10:38
登山道出口に到着した。
ここから暫くは林道を歩く。
日差しがかなり強くなってきた。
|

11:04
暑い林道歩きだが、キヌガサソウやタマガワホトトギスなどの
初見の花も多く、撮影しながら歩く。
右手に標識が現れた。
“鑓温泉”への登山口を通過する。・・・(G地点)
|

「中部山岳国立公園-猿倉」の石碑
|

11:08
林道から再度、林の中に入る。・・・(H地点)
|

朴の木などが生えて癒される森を通過する。
|

右手に小屋が見えた。
|

11:15
終点の“猿倉荘-下山口”へ全員無事に下山してきた♪
ここで6人グループの皆さんと握手をしてお別れする。
|

“猿倉荘”全景
|

初の北アルプスを無事に歩けたことを記念して
祝杯を挙げる\(^o^)/
|

“白馬山荘”の弁当はまずまずだった♪
(到着地点でも都合は付くが非常食のつもりで携帯した)
|

バスの時間までは1時間ほどあるとのことなので
又々、タクシーで“白馬ロイヤルホテル”まで戻る。
ホテルで3日振りの風呂に入り汗を流してサッパリしたところで
“JR白馬駅”まで徒歩で向かう。・・・(徒歩3分)
ここで千葉から来られたご夫婦と再会。
挨拶を交わしてお別れする・・・お世話になりました<(_ _)>
|

どこの駅のベンチも木製でお洒落だった。
|

特急“あずさ号”・・・・・JR松本駅にて
新宿行か?
|

登山者の群れ・・・・・JR松本駅にて
九州では見れない光景だ。
|

特急“ワイドビューしなの22号”・・・・・JR松本駅にて
|

夜行バス“どんたく号”・・・・・JR小倉駅前バス停にて
|
● 総 括 ●
今回は初めての北アルプスをカミサンと二人で歩くということでもあり、体力・日程的に十分余裕を持った計画を立てた。
その分、出費は増えたが保険を掛けたと思い、おかげで無事に帰宅できたと考えれば結果として無駄ではなかったとしておこう(笑)
歩行中は霧の発生が多く景観的には残念な場面が多々あったが、途中、雨や雷にあう事も無く屋久島に続いて幸運であった。
視界の悪い霧の中の歩きや、“白馬山荘”では夕方から夜半までの雷雨も経験し、山の変わり易い天候も身を持って体験できた。
山小屋泊で軽装備なら高山植物の撮影は絶対に一眼レフは外せないという思いから、
6月から7月に掛けてほぼ毎週行った山歩きは暑さの中を辛抱して、アルプス用装備にプラスアルファの負荷で常に13~14kgを担いだ。
効果も十分だったようで、本番では11kgに設定した今回の装備は体力的に特に負担に感じずに済んだ♪
・・・・・やはり、山行内容に合わせた計画的な体力作りは重要だと改めて感じた山行でもあった。
そして、何と言っても個人で計画し、実行してほぼ山行コンセプト通りにやり遂げたことに、
アルプスデビューできたという表面的な事実以上の大きな喜びと意義を感じる。
ツアー,グループと山行スタイルは人それぞれ様々ではあるが、個人での山行にはこれらでは体験できないものがある。
まずは、カミサン以外は相談者はいないという事から心の中の弱い部分である依頼心が薄れる。
現地では全ての行動に於いて文字通り自己責任の下での個人での判断力・決断力が不可欠になる。
今回のコースはアルプスを目指す登山者が比較的容易に足を踏み入れることが可能な初心者向けの入門コースとして紹介されている。
それでも初めてのアルプスともなると本当に自分達だけで行けるのかと不安はかなりのものだった。
そんな初めてのアルプスを個人計画で実施できたことは、大袈裟に例えるならば何れのスポーツでも一度しかチャンスが巡ってこない
新人賞を運良く手中にしたような、そんな満足感・達成感を得ることのできた貴重な山行でもあった・・・♪◎♪
|

|