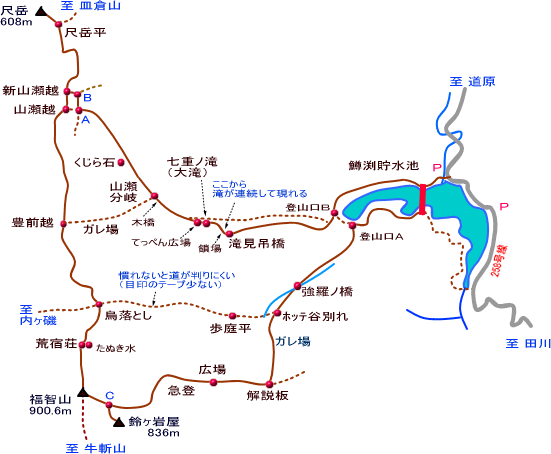8:00
鱒淵ダム堰堤傍の車道脇に車を止めてスタートする。
新装されたダムの設備を眺めながら堰堤を渡る。
(参加はMORIさん、カラスさん、シュー左衛門さんご夫婦、我々夫婦の6名) |

ダム周回路に咲いていた梅の花 |

紅白揃って目出度い(^^♪ |

ダムを周回する舗装路歩きは退屈で辛いところだが
例会ともなると人数が多く話が弾むので、
普段は長いと感じる約30分があっと言う間だ。♪ |

8:31
“七重の滝コース”の登山口に到着。(登山口B)
このコースは最初から沢沿いを歩くことになる。
夏の暑い日などは沢の音が清涼感に溢れなかなか良い。 |

案内標識 |

8:36
最初の橋には“七重の滝入口橋”の名前・・・・・
何度も歩いているのに初めて気付いた(^_^;) |

“七重の滝入口橋”を渡ると沢を右に見ながらの歩きになる。 |

8:48〜57
沢に掛かった三つ目の橋(滝見吊橋)を渡ると
このコースの見所である最初の滝(一の滝)に着く。
ここで小休憩とする。
|

一の滝 |

8:57
約10分の休憩後、コースの最初で最後の難所の約10mの鎖場を登る。 |

それほどこのコースは危険箇所も少なく、コースさえ覚えれば
安心して山歩きが楽しめる。
山歩きを初めて間もない人が体力アップを図るには持って来いのコースだ。
鎖場の通過がどうしても怖い人は左手の巻き道を利用しても良い。 |

二の滝 |

唯一コースの左手にある滝。
名前は?・・・ |

三の滝 |

五の滝 |
 |
沢沿いの急傾斜のキツサも次々に現れる
八つ?の滝を見ながらの登りで気が紛れる。
(五の滝の傍を通過中)。
|

このコースの最後の滝だ。
私の中では一番形の良い滝だと思っている。
|

七の滝(大滝) |

9:22
“てっぺん広場”に到着。
ここは急傾斜を頑張って「ヤレヤレ」と一息つくには持って来いの場所だ。
|

9:27
橋を渡って僅かに登ると幅広の林道に出る。
かっては荷馬車も通っていたらしい。
右に進むと今歩いてきた登山道の巻き道になっている。
七重の滝コースの沢が増水して危険な際は
この巻き道を利用すると良い。
ここは、左に進む。 |

ここからのコースが又良い。
見上げる空も青空が広がってきた♪ |

水辺のセキショウや秋は数輪の彼岸花が目を楽しませてくれる。
注意深く見るとチョッと良い花も咲いている。
急傾斜を登り上がった後、アップダウンがない沢沿いの道が続く
不思議な空間だ。 |

9:38
二つ目の木橋を渡ると“山瀬別れ”に着く。
ここを左に進むと九州自然歩道の“豊前越”に登り着き、そこを左で
“福智山”へ行ける比較的コンパクトな周回コースになる。
山歩きを始めたばかりの人へのおお薦めコースだ。
今回は、ここを真っ直ぐに進んで“尺岳”を目指す。
|

最初は杉の美林を歩く。 |

9:48
ジワジワと高度を稼ぐと左手に“くじら石”が現れる。
言われてみれば確かに鯨に見える。 |

10:04
更に進むとようやく林を抜けて林道に出会う。(A地点)
林道を横切り真っ直ぐ登り上がると、九州自然歩道の
“山瀬越”に登り着き、そこを左で“福智山”へ行ける。
周回コースが“豊前越〜山瀬越”の距離ほど長くなる。
今回はここを林道を歩いて右に進む。 |

10:16
林道を進み途中の右への分岐(B地点)を見送って更に進む。 |

10:18
九州自然歩道と交差する“新山瀬越”に出会う。
ここを右に進む。
九州自然歩道を皿倉山方向に向かって歩くことになる。 |

九州自然歩道の入口には柵が設置されている。 |

まだまだ元気です。 |

10:35
約20分(1.2km)で立派なあずま屋のある広場に到着する。
“尺岳平”だ。
カラスさんが「屋根の色が違うー」と言う。
自分が初めて歩いた2004年は既にブルーだったが
カラスさんが歩かれた2001年は茶色っぽい色だったようだ(~o~) |

10:40〜55
“尺岳平”を直進して僅かに登り上がると
この日の最初の目的地である“尺岳”山頂に着く。 |
 |
好天の山頂で晴れやかに記念撮影だ。 |

この日は視界も良く雄大な眺めを楽しめた。♪
山頂からは北の方向を見ると遥か彼方に
昨年の縦走の起点になったアンテナが林立する
“皿倉山”と“権現山”がハッキリと見える。 |

反対側に目を転じるとこれから向かう“福智山”も聳えている。
これまで3度ほどここに来ているがこれほど視界が良いのは
初めてだ。 |

“尺岳”を後にして5.3km先の“福智山”を目指す。
道幅が狭くなると一列渋滞になるので無言で黙々と歩く。 |

11:06
“竜王峡”への分岐を通過。 |

多くの登山者に踏み込まれた九州自然歩道(稜線上)の
快適な歩きが続く。 |

11:15
あっと言う間に“新山瀬越”まで戻ってきた。 |

“新山瀬越”標識 |

まだまだ元気です。 |

11:24
“山瀬越”を通過。
|

11:45〜12:26
アップダウンの少ない縦走路を進み
急な下りが終わると“豊前越”に到着。
頃合も良くここで昼食とする。 |

日溜まりのテーブルで賑やかに昼食だ。
しかし、風が吹くとさすがに寒い(>_<) |

この日一番のメニューは
やはりシュー左衛門さんご夫婦の
“卵入り雑炊”だ(^^)// |

12:31
お腹も膨らみ落ち着いたところで“烏落とし”を目指す。
ここからは緩やかだが登り主体の道が続く。
体力不足だとそろそろキツクなってくるところだ。
このところ体調不備で歩き込めてなかったので心配だったが何とか歩けた。
この日は例会オーナーということで気合も入っていたようだ(~o~)
縦走路に残雪が目立ち始めた。
|

12:52〜13:00
“烏落とし”もホンノリと雪化粧だ。
落葉樹が多いせいかいつもより広々と感じた。 |

後続も元気に到着。
チャコちゃん(シュー左衛門さんご婦人)も
このところ体力アップされて元気一杯だ。 |

“烏落とし”で小休憩後、更に進む。
ここから“福智山”山頂までは約200mの登りだ。
傾斜も急になる。
道も若干凍結気味になってきた。
アイゼンは登りなので装着しなかった。 |

13:08〜13
“たぬき水”の冷たい水でで喉を潤し“荒宿荘”に着いた。
ここは最近になってバイオトイレも設置され“福智山”を愛する登山者達の
憩いの場所になっている。
|

ここからも“皿倉山”と“権現山”が良く見えた。 |

“荒宿荘”で小休憩後、最後の目的地である“福智山”山頂に登る。
ここからも時間は短いが胸突き八丁のなかなかの急傾斜だ。
残雪が凍りついている。
滑らないようにと用心深く一歩一歩歩いていたら
キツイと思う間もなく、いつの間にか山頂に着いた(^^ゞ
|

13:28〜45
青空を背景で記念撮影・・・・・♪ |

山頂はいつも通りの強風が吹いている。
温度計は4℃だが体感温度はかなり寒い。 |

山頂からの視界も良い。・・・八丁方向 |

鱒渕ダム方向 |

“貫山・平尾台・龍ヶ鼻”方向 |

13:45
大岩の影で風を凌いで暫し休憩後、下山に掛かる。
登山口まで3.7kmだ。 |

下山は“鈴ヶ岩屋”方向へ下る九州自然歩道コースとした。
こちらの道は雪が殆ど無い。 |

13:56
“鈴ヶ岩屋”にも登って行こうと話しが纏まり立ち寄る。
ここから脇道に入る。(C地点) |

柘植の木とサルトリイバラ、そして棘のあるノイチゴか?
とにかく引っかかって歩きづらい。 |

14:02〜05
“鈴ヶ岩屋”には平たい岩場があったが標識は無いようだった。 |

下山してきた“福智山”の眺め。 |

五徳峠への縦走路が見える。
その向うに“英彦山・鷹ノ巣山”も見えたが
画像では判りづらいのが残念。 |

13:00
“福智山”を背景に・・・・・ |

“鈴ヶ岩屋”を後に九州自然歩道を下る。
木段の滑り易い道を注意深く下る。
この辺りは名残の雪もチラホラだった。 |

14:27
このコースの最初の休憩ポイントである
“大杉渡り”まで一気に下る。 |

14:27〜32
道に岩ゴロが多くなってくると沢(大杉渡り)が現れ、
これを渡ると大杉とベンチがある休憩所広場に着く。
ここで小休憩・・・・・ |

14:45
“大杉渡り”の休憩所からは暫くは傾斜も緩い歩き易い道になる。
アカガシ林の“解説板”のある尾根の肩に到着。
ここにもベンチがあり、ここから左折して下る。 |

“福智山”から1.8kmの標識 |

ガレ場を2箇所慎重に通過する。 |

15:01
前方が開けてくるとやがて“ホッテ別れ”に着く。
ここは“烏落とし”へとホッテ新道コースで繋がっている。
ここまで来れば歩き難い道も残り僅かだ。 |

“ホッテ別れ”標識 |

15:05〜15:15
僅かで“強羅橋”だ。
ここは雨の後などは増水して渡渉に苦労することもある。
傍のベンチで休憩をとる。 |

このあとは右手に深い谷を見ながら植林帯に沿って付けられた道を下る。
この傾斜が疲れた膝には結構堪える。
途中、あと僅かで開花するミツマタがあった。 |

15:38
ベンチの設置された登山口に到着。(登山口A)
七重の滝コースの登山口(登山口B)はここから数分の場所だ。
ここからの舗装路歩きも約30分を要するので疲れた足には辛いところだ。 |

九州自然歩道の案内標識板・・・(登山口A) |

鱒淵ダムに掛けられた赤い橋が見え始めた。 |

15:55
鱒淵ダムに掛けられた赤い橋まで来ればゴールも近い。
この日のコースは17〜18kmはあるだろうか?
16:00ジャストに全員無事に車まで戻ってきた。
昨年の11月頃から体調不備なことが多く長距離の歩きをしてなかったので
この日もどの程度歩けるか気掛かりだったが何とか歩き通せて
ホット一息の山行であった。
皆さん、お疲れ様でした。 |

|